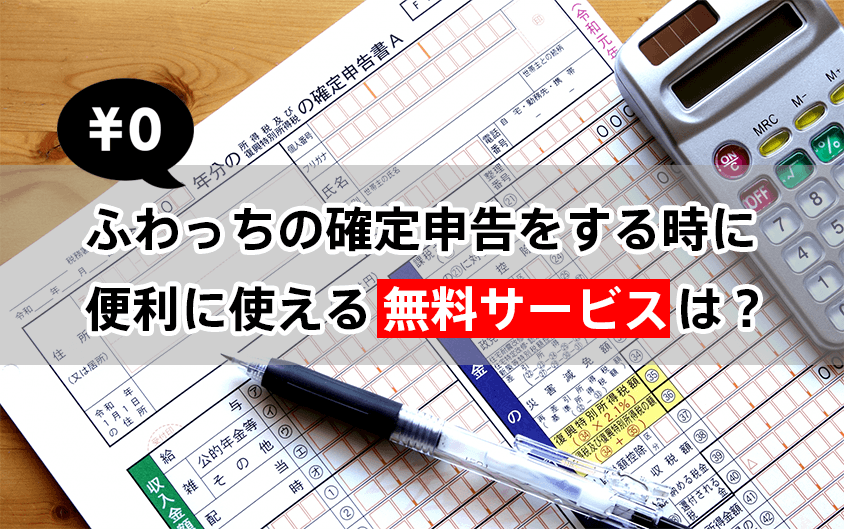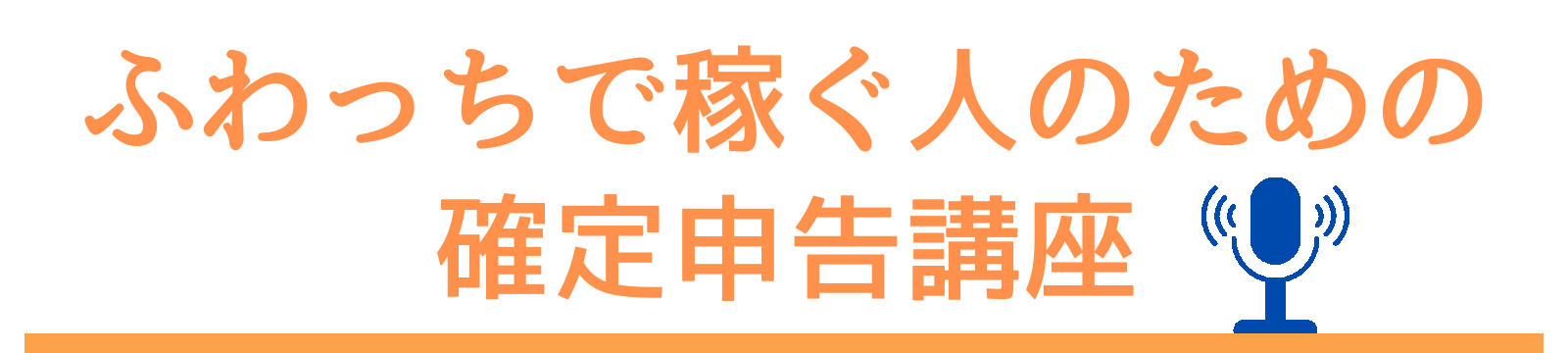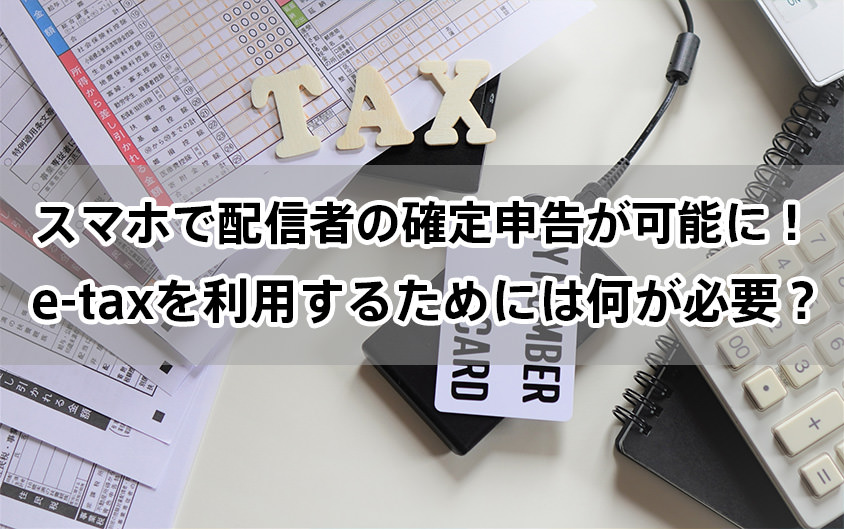令和元年分の確定申告から、スマホ申告の対象が拡大されます。
スマホ申告にはいくつかの条件はあるものの、
課税所得のある配信者の多くも準備さえすれば利用できる内容なので紹介します。
来年2月から始まる令和元年分の確定申告から、
【雑所得】のスマホでの確定申告対応がスタートします。
例えば、所属事務所があって源泉徴収された報酬を貰っているようなこともなく、
所得区分も事業所得ではなく雑所得で申告しているという配信者は多いはず!
申告している人は「雑所得で白色申告してます」という人がほとんどですよね。
そこで、スマホを使ってe-tax(電子申告)するために必要な準備を紹介します。
スマホで雑所得の確定申告するために必要な準備

スマホで確定申告を行うためには、次の2種類の方法があります。
- マイナンバーカード方式…マイナンバーカードを使った確定申告
- ID・パスワード方式…IDとパスワードを使った確定申告
マイナンバーカードを持っているかどうかで方式を選ぶことになりますが、
どちらを選んでも予めの準備が必要です。
マイナンバーカード方式でのスマホ申告の準備

マイナンバーカード方式という名称の通り、
まず大前提として「マイナンバーカード」が必要になります。
そして、そのマイナンバーカードを読み取るためのスマホについては、
お使いのスマホの機種によってe-taxの送信方法が違います。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホがある場合
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホがある場合は、
スマホ本体とマイナンバーカードで申告ができます。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホについては、
「マイナンバーカード読み取りに対応したスマホ」でご確認下さい。
あとは、Android、iPhoneともに「マイナポータルアプリ」をインストールするだけで、
e-taxが利用できます。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホがない場合
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホがない場合は、
スマホをICカードリーダーとして利用することでパソコンやタブレットから申告できます。
以前はICカードリーダーの機器が必要でしたが、現在はスマホで代用できます!
こちらの場合はマイナポータルアプリと連携させて申告します。
ID・パスワード方式でのスマホ申告の準備
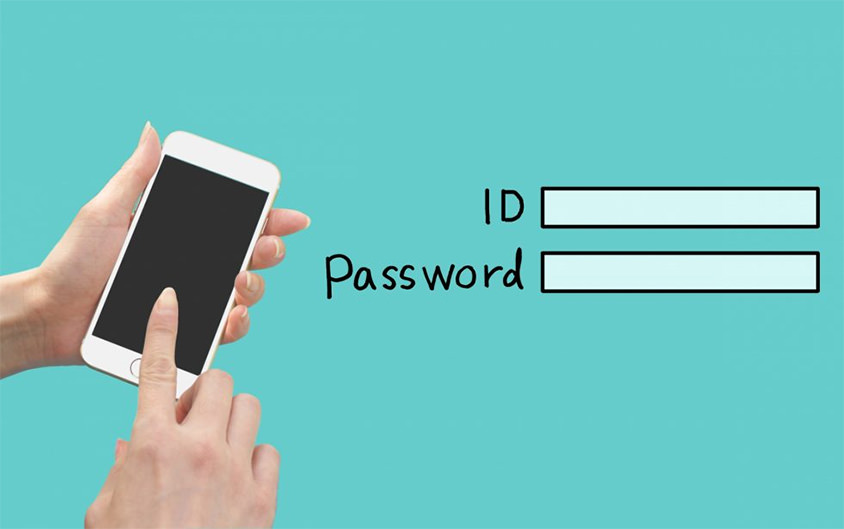
マイナンバーカードが無い人は、ID・パスワード方式で申告できます。
ただし、ID・パスワード方式については、申告までに税務署に一度足を運ぶ必要があるので注意して下さい。
税務署の窓口で職員に免許証などの本人確認書を提示すれば、
「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらえます。
あとはその「届出完了通知書」に記載のe-Tax用IDとパスワードを利用することで、
e-Taxの利用が可能です。
スマホを使った確定申告の方法
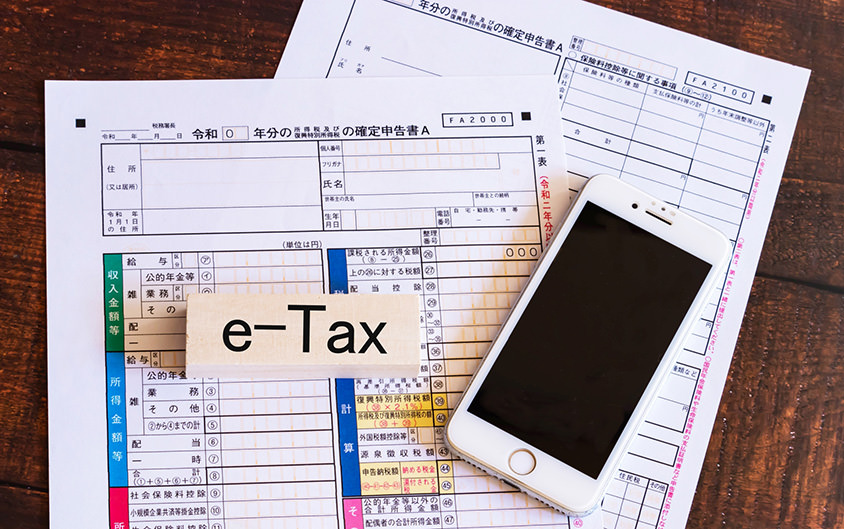
最近のe-taxはとても分かりやすくなっていて、
質問に回答をしていくだけで確定申告書が自動的に作成されていきます。
以前は「確定申告=事業者」というようなイメージが主でしたが、
近年はふるさと納税の関係で確定申告をする人も増えていて一般化が進んでいます。
実際、だいぶと分かりやすく申告できるようになっていますよ。
スマホとマイナンバーカードを使ったe-taxでの申告を希望している方は、
以下のページより詳細を確認して下さい。
![]() スマートフォンとマイナンバーカードを使ったe-taxの手順の詳細はこちら!
スマートフォンとマイナンバーカードを使ったe-taxの手順の詳細はこちら!
スマホ申告のデメリットも紹介します

税務署に行かなくてもスマホから簡単に確定申告ができるスマホ申告ですが、
e-tax(電子申告)ならではのデメリットもあります。
税務署に足を運んで窓口で申告をする場合は相談窓口があったり、
簡易的なミスであれば受付時に職員が修正を指摘してくれます。
一方で、スマホ申告の場合は税務署職員と顔を合わせた相談ができません。
仮に不備があった場合でもそのまま受付が完了されてしまうので、
後ほど税務署から連絡が入り修正申告が必要になる場合も…。
そうなれば、便利なスマホ申告をしたばっかりの二度手間です。
そのような万一のリスクも伴うので、「e-taxの質問で聞かれていることの質問の意味さえ分からない」というようなレベルの人にはあまりおすすめしません。
e-taxを利用しない場合の確定申告の参考リンク
スマホ申告やe-taxを利用せずに確定申告をする場合は、
確定申告書を作成して税務署に直接持っていくことになります。
ネットで申告書が作成できる国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、
あくまで確定申告書の作成だけなので帳簿の作成はできません。
記帳は別で行っている場合はそれでもいいかもしれませんが、
やはり記帳から確定申告書の作成までを一本化させたほうがスリムです。
管理も楽になるのでおすすめです!
その場合は「やよいの白色申告オンライン(無料)」を使うことで、
記帳から確定申告書の作成までを一本化できます。
完全無料で利用できるので、よければ以下の記事も参考にしてみて下さい。